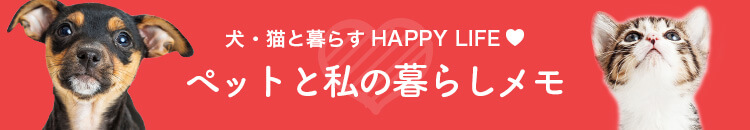犬に寄生するマダニとは?症状や病気・対処法・予防方法を解説

ワンちゃんに必要な予防といえば、フィラリア、ノミ、マダニ、狂犬病、混合ワクチンです。
今日はその中でも、これから暖かい季節になっていくと活動が活発になる「マダニ」についてお話したいと思います。
アイペット損保のペット保険は
12歳11か月まで新規加入OK!
ニーズに合わせて2つの商品から選べる
犬に寄生するダニとは?

「ダニ」と聞くと、布団やカーペットに生息しているダニを想像する方が多いかもしれません。
ダニは主にヒョウヒダニ(チリダニ)と呼ばれる種類で、人間のフケやほこりを餌に生活しています。
一方、ワンちゃんに寄生して吸血し、さまざまな病気を媒介するのは、「マダニ」と呼ばれるダニです。
ヒョウヒダニは肉眼では見えないほど小さいですが、マダニは肉眼で確認できる大きさです。
犬に寄生するダニの種類
ワンちゃんに寄生するマダニの中でも、日本で多くみられるのは「フタトゲチマダニ」という種類です。
マダニ以外にも、「ニキビダニ」や「ヒゼンダニ」という、ワンちゃんに皮膚炎を引き起こすダニも存在します。
大きさは?
マダニは目に見えるサイズで、吸血していないときは、大人のマダニで約3~8mm、吸血したときには、その10倍ほどに膨れ上がることもあります。
どこにいるの?
公園、河川敷、草むら、森、山など、緑が多く適度な湿気のある環境を好み生息しています。
葉っぱの裏側など、寄生できる動物が近づいてくるまでじっと待ち構えています。
ワンちゃんのお散歩コースとしては自然の多い所を選んであげたくなりますが、マダニが潜んでいる可能性があることも知っておきましょう。
好きな季節は?
マダニは、暖かい春から秋にかけて活動が活発になります。
活動のピークは10月~11月頃ですが、種類によっては冬に活動が活発になるマダニもいるので、基本的には一年中警戒する必要があります。
マダニがつきやすい身体の場所は?
マダニは、目・鼻・口の周り、耳、胸、お尻の周り、内股などの毛が薄い部分につきやすいです。
ワンちゃんはお散歩で草むらに顔を近づけることも多いので、特に顔周りは注意して見てあげましょう。
マダニのライフサイクル

マダニの一生は、卵からかえり、成長して大人になる、という単純なものではありません。
卵からかえると、吸血と脱皮をくり返しながら、幼ダニ→若ダニ→成ダニと成長していきます。
メスの成ダニは、動物の体温や二酸化炭素を感知して寄生します。
飼い主さまが気付かなければ何日も、ときには数か月以上吸血し続けることもあります。
そして十分に吸血すると地上に落下して卵を産み、一生を終えます。
多い時には2,000~3,000個もの卵を産むといわれています。
マダニの寄生によって起こる病気や症状

マダニの寄生で怖いのは吸血だけではなく、咬みつかれたときにマダニが運んでいる細菌やウイルスが動物の体に侵入してしまうことです。
貧血
マダニは頭を動物の皮膚に食い込ませて咬みつくので、一度寄生してしまうとなかなか離れてくれません。
飼い主さまが気付かずに長期間たくさんのマダニに吸血されると、貧血を引き起こしてしまうことがあります。
貧血になると、元気や食欲がなくなり、お口の中の粘膜が白っぽくなることがあります。
ダニ麻痺症
マダニの種類によっては毒性物質を分泌するものがいます。
そのようなマダニに吸血されることで、ワンちゃんの体内に毒性物質が入り、筋肉が麻痺してしまう病気です。
足が脱力してふらついたり、顔の筋肉が麻痺して緩んだりします。
このような神経毒を分泌するマダニは、アメリカやオーストラリアに多く生息しています。
バベシア症
マダニが媒介するバベシアという原虫がワンちゃんの体内に入り込み、赤血球に寄生して破壊することで貧血を引き起こす病気です。
2~3週間の潜伏期の後、食欲の低下や発熱、黄疸、血色素尿(赤褐色のおしっこ)などの症状があらわれます。
重症化すると多臓器不全に陥り、命に関わることもあります。
バベシア症は西日本で比較的多く発生していましたが、近年では温暖化の影響もあり東日本での感染もみられるため、全国的に注意が必要です。
重症熱性血小板減少症候群(SFTS)
SFTSウイルスを運んでいるマダニに咬まれることで感染する病気です。
ワンちゃんは感染しても無症状であることが多いです。
人間に感染すると、約6日~2週間の潜伏期の後、発熱や消化器症状、頭痛、筋肉痛、神経症状、皮下出血や下血などが認められ、命を落とすこともある恐ろしい感染症です。
SFTSウイルスに対するワクチンや有効な治療法は見つかっていないため、予防がとても大切です。
ライム病
マダニが媒介するボレリアという細菌によって引き起こされる病気です。
日本では北海道で比較的多く発生しています。
ワンちゃんでは目立った症状がないことも多いですが、元気や食欲がなくなり、ふらつきがみられることもあります。
人間に感染すると、マダニに咬まれた部分から徐々に紅斑が広がる「遊走性紅斑(ゆうそうせいこうはん)」や発熱、関節痛、筋肉痛、倦怠感など症状があらわれます。
Q熱
マダニが媒介するコクシエラという細菌によって引き起こされる病気です。
ワンちゃんは感染しても無症状であることが多いです。
人間では高熱や頭痛、筋肉痛、倦怠感といったインフルエンザのような症状が出て、肺炎や肝炎を引き起こすこともあります。
エールリヒア症
マダニが媒介するリケッチアという細菌の一種によって引き起こされる病気です。
ワンちゃんでは発熱、体重減少、出血などを引き起こします。
ワンちゃんに寄生するエールリヒアは人間にはうつりませんが、人間に感染するエールリヒアも存在しています。
日本紅斑熱
1984年に徳島県ではじめて報告された病気で、リケッチアの一種によって引き起こされます。
動物での症状は明らかになっていませんが、人間では高熱、頭痛、倦怠感、全身の紅斑(発疹)が認められ、重症化すると多臓器不全を引き起こし命に関わることもあります。
近年では感染地域の拡大や患者数の増加もみられているため、注意が必要です。
犬の身体にマダニを見つけたら

マダニは頭を皮膚に食い込ませているため、むやみに引っ張ると、頭部だけがワンちゃんの体の中に残ってしまう可能性があります。
また、細菌やウイルスを運んでいることもあるため、潰してしまうのも危険です。
マダニを発見したら、早めに動物病院で処置してもらいましょう。
マダニの予防策

投薬
マダニ予防として一番効果的なのは、お薬を使うことです。
マダニの駆除薬には、液体を垂らすスポットタイプや、おやつのように食べるチュアブルタイプがあります。
マダニと同時にノミ、フィラリア、お腹の寄生虫などもあわせて予防できるお薬もあるので、ワンちゃんの体質や生活に一番合うものを動物病院で選んでもらいましょう。
ブラッシング
ブラッシングをすると、マダニを早期に発見しやすくなり、皮膚の健康も促進することができます。
特にお散歩から帰ったときにしっかりブラッシングをしてあげることで、吸血する前のマダニを落とすことができるかもしれません。
定期的なシャンプー
シャンプーもブラッシングと同じように、マダニを発見することができ、皮膚を清潔に保つことにもつながります。
ワンちゃんの皮膚や被毛の状態にもよりますが、月に1~2回はシャンプーをしてあげられると良いですね。
身体をよく触る
外出から帰ったときなどは、マダニがつきやすい毛の薄い部分を中心にワンちゃんの身体をよく触って、マダニがいないか確認しましょう。
身体を触ってはじめて、しこりなどを発見できることもあるので、意識して触ってみましょう。
散歩のコースや服装に注意する
お散歩コースから公園などを外す必要はないですが、ぐいぐいと草むらに入っていくのは避けた方が良いかもしれません。
飼い主さまは長袖の服を着用して皮膚の露出を少なくする、ワンちゃんにも洋服を着せてあげると、マダニの付着を防ぐことができます。
おうちの環境を整える
マダニは肉眼で見える大きさではありますが、気付かないうちにおうちに入り込んでいる可能性は十分にあります。
お部屋は掃除や換気を行って常に清潔な状態を保ち、ワンちゃんの使っているベッドや毛布も定期的に洗うようにしましょう。
まとめ

マダニはワンちゃんだけではなく、私たち人間にとっても恐ろしい存在です。
ワンちゃんのマダニ予防を行うことは、飼い主さま自身を危険な感染症から守ることにもつながります。
マダニは常に私たちのすぐそばに潜んでいると考え、対策をしっかり行いましょう。
アイペット損保のペット保険は
12歳11か月まで新規加入OK!
ニーズに合わせて2つの商品から選べる