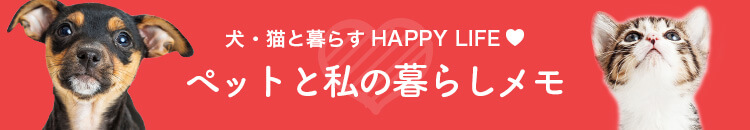猫の口内炎の原因や治療法、予防について獣医師が解説!

猫も人と同じように口内炎を発症することがあります。
猫の口内炎は口の中全体に広がりやすく、治療が難航しやすい病気とされています。
ここでは、猫の口内炎について原因や治療法、予防について解説します。
アイペット損保のペット保険は
12歳11か月まで新規加入OK!
ニーズに合わせて2つの商品から選べる
猫の口内炎とは?

猫の口内炎の定義は、「口腔の内側を覆っている粘膜の炎症で、歯肉炎や歯周炎にとどまらず、粘膜下まで広がっている口腔の炎症である」とされています。
口の中の粘膜が炎症し、歯肉や舌、頬の内側などに痛みや出血を引き起こす病気です。
猫の口内炎の原因

感染症
主な原因の一つに、ウイルスや細菌による感染症があります。
猫の口内炎に関与するウイルスは、「猫カリシウイルス」「猫ヘルペスウイルス」、免疫力を低下させる「猫免疫不全ウイルス感染症」「猫白血病ウイルス感染症」が代表的です。
免疫の異常
腎臓病や糖尿病などの病気で免疫力が低下したときに、口内炎が発症することがあります。
また、口の中の細菌に対して免疫が過剰に働くと炎症が起こる場合もあります。
口の中の病気
食べ物の歯石が堆積すると、その表面に多くの細菌やウイルスが付着し症状が悪化する場合があります。
口腔内細菌も一因となるため、定期的に歯磨きをしてあげましょう。
口内炎を発症しやすい猫種は?
口内炎は猫種や年齢に問わず発症します。
感染症が原因となることもあるので、混合ワクチンを接種していない場合や、外でほかの猫と触れ合う機会がある場合はリスクが高くなります。
猫の口内炎の症状

以下のような症状が見られる場合は、動物病院で相談することをおすすめします。
疼痛(とうつう)
猫の口内炎に共通する症状は、疼痛(とうつう)、つまり痛みです。
ごはんを食べたがらない、口をくちゃくちゃさせる、口周りを触られるのを嫌がる、毛づくろいの頻度が減る、性格が攻撃的になるなどの仕草は痛みのサインかもしれません。
流涎(りゅうぜん)
口内炎が進行すると、よだれの量が増えてきます。
さらに症状が進行すると、口の中で出血が起こり、血混じりのよだれが出ることもあります。
口臭
口腔内細菌が増えることで口臭が強くなります。
猫は毛づくろいをする生き物であるため、口臭のにおいが全身についてしまうこともあります。
食欲低下、脱水
猫は、身体に違和感があると食欲が低下する傾向があります。
フードからの水分摂取が困難になると、脱水を引き起こしてしまう場合もあります。
慢性的に食欲がなくなると体重も減少するので、体重はこまめにチェックするようにしましょう。
猫の口内炎の治療法

猫の口内炎の治療法には、大きく分類すると、外科治療と内科治療があります。
口内炎は完治が難しい場合もありますが、原因となる疾患の治療をしながら、痛みや炎症を抑え、口腔内細菌を減らす治療を行います。
外科治療
外科治療は全身麻酔を使用するため、血液検査やX線検査によって、全身麻酔に耐えられるのか検査します。
血液検査では、腎機能や肝機能、貧血の有無などを調べ、場合によっては内分泌疾患の評価も同時に行います。
X線検査は、単純X線検査と歯科用X線検査の2種類あり、全身の状態や歯の状態を把握することが目的です。
例えば歯周病の場合、腔内の細菌を少なくコントロールし炎症を抑える治療法として、抜歯が有効とされています。
抜歯には汚れが蓄積しやすい奥歯をすべて抜く全臼歯抜歯(ぜんきゅうしばっし)と、すべての歯を抜く全抜歯があります。
口臭がある場合は、歯石や歯垢を除去する治療もあわせて行われることがあります。
全身麻酔が必要になるので、口内炎の状態だけではなく、猫の年齢や体調も考慮する必要があります。
内科治療
抗生剤などの内服薬によって、炎症や痛みを抑える治療です。
内科治療は、外科治療が行えない場合や外科治療の補助として行われることが多いです。
再生医療
外科・内科治療に反応がない場合や、外科治療が難しい場合は、細胞治療という選択肢もあります。
培養した細胞を猫に投与することで、炎症を抑え、免疫力を高めるなど細胞組織の修復を促します。
予防法

混合ワクチンを接種する
口内炎の原因となる感染症の予防につながるため、定期的に混合ワクチンを接種しましょう。
歯磨きを行う
口の中を綺麗に保つには、歯ブラシによる歯磨きが一番有効です。
口を触られるだけで嫌がる猫も多いので、子猫のうちから練習するようにしましょう。
歯ブラシは猫用の小さなものを使い、歯と歯肉の間の歯垢をかき出すように磨いてあげるのがポイントです。
歯ブラシが難しい場合は、指にガーゼを巻き付けて磨いたり、歯肉のマッサージをしてあげましょう。
デンタルグッズを活用する
歯磨きを嫌がる猫の場合は、デンタルケアができるおやつやおもちゃを活用しましょう。
口内環境の改善や免疫力を高めるサプリメントを与えることもできます。
まとめ

口内炎を発症すると、ごはんが食べられない、毛づくろいができないなど、猫に大きなストレスがかかります。
口内炎の治療は難航しやすいため、定期的に歯磨きを行い予防しましょう。
ごはんを食べたがらない、口臭が強くなるなど、普段と異なる様子がみられたら動物病院で相談しましょう。
アイペット損保のペット保険は
12歳11か月まで新規加入OK!
ニーズに合わせて2つの商品から選べる