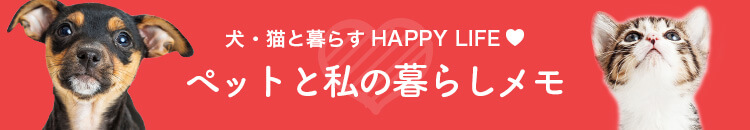猫の膿皮症とは? 症状・原因・治療法などを獣医師が解説

猫の膿皮症(のうひしょう)は、皮膚病の一つです。
猫がしきりに体をなめたり掻いたりする様子や、赤みを帯びた発疹、皮膚のめくれなどが見られる場合は膿皮症かもしれません。
原因は細菌による感染ですが、発症するかどうかは体調に左右される面もあります。
犬に比べると猫の発症は少ないといわれていますが、愛猫の健康のためにも膿皮症について理解を深めておきましょう。
アイペット損保のペット保険は
ニーズに合わせて
2つの商品から選べる
猫の膿皮症ってどのような病気?

猫の膿皮症について、主に見られる症状と、かかりやすい猫の種類について説明します。
どのような症状が出るの?
猫の膿皮症の主な症状は、かゆみや痛み、赤みのある発疹や皮膚のめくれです。
かゆみや痛みは、猫が体をなめたり掻いたりする様子から判断することができます。
- しきりに体をなめる、掻く
- 赤い発疹
- 円状に薄く皮膚がめくれる
膿皮症の症状の一つとしてよく見られるのが、かゆみです。
猫がしきりに体をなめたり掻いたりする様子が見られたら、かゆみがあると考えてよいでしょう。
あまりにもなめすぎたり掻きすぎたりすると皮膚の状態が悪化し、痛みを感じるようにもなります。
愛猫が体の一部をしきりになめたり掻いたりしているときは、被毛を掻き分けて異常が起きていないかどうかを確認してみてください。
膿皮症では、皮膚が炎症を起こし、赤くぶつぶつとした発疹が見られることもあります。
炎症がひどくなると膿をもち、白く小さな発疹となって現れます。
ふくらんだ発疹部分の皮膚は盛り上がって薄くなっているため、なめたり掻いたりしすぎると、皮膚が破れてめくれた状態になってしまいます。
皮膚がめくれると同時に、脱毛を伴うこともあります。
皮膚のめくれや膿んだ状態が広範囲に及ぶと、皮膚がじゅくじゅくする、炎症の悪化で出血する、脱毛箇所が広がる、かさぶたができるなど、皮膚の状態がどんどん悪化してしまうので注意が必要です。
かかりやすい猫の種類
ヒマラヤンやペルシャは、皮膚糸状菌症(ひふしじょうきんしょう)を発症しやすいです。
この皮膚糸状菌症がもとになって、膿皮症を引き起こす可能性があるため、注意が必要な猫種といえるでしょう。
また、猫の種類には関係なく、体の機能が未熟な子猫、免疫力が下がっている猫、体力が落ちている高齢の猫、クッシング症候群*や甲状腺機能低下症などの内分泌系の疾患をもった猫、アトピー性皮膚炎のようなアレルギー性疾患のある猫もかかりやすいといわれています。
*副腎皮質機能亢進症(ふくじんひしつきのうこうしんしょう)とも呼ばれます。副腎という臓器から、コルチゾールというホルモンが過剰に分泌されることで発症します。
猫の膿皮症の原因

猫が膿皮症を発症する主な原因は、ブドウ球菌による感染です。
ただし、ブドウ球菌は皮膚に常在する菌なので、菌があれば必ず発症するというわけではなく、発症に至るには要因があります。
例えば、風邪などをひいて免疫力が低下したときは、皮膚のバリア機能が弱くなったり細菌バランスが崩れたりして発症しやすくなります。
ノミやダニ、食べ物、花粉やほこりなど環境要因によるアレルギー疾患も原因の一つです。
皮膚糸状菌症、マラセチア性皮膚炎など、ほかの皮膚疾患から膿皮症になるケースもあります。
内分泌系の疾患(クッシング症候群、甲状腺機能低下症など)を持っている場合も発症しやすいとされています。
膿皮症は高温多湿となる時期に増える病気であり、環境面の要因も大きいです。
猫の膿皮症の治療法

猫が膿皮症になったときの治療は、原因菌に対する抗生物質の使用とシャンプーを行うのが一般的です。
抗生物質による治療
原因菌に直接アプローチできる抗生物質を含んだ内服薬、および塗り薬を使い、体の内側と外側から治療します。
抗生物質の内服薬は、獣医師の指示にしたがい、処方された分を飲みきるようにしましょう。
薬を飲ませることが難しい場合は、一定期間効果が持続する注射を投与する方法もあります。
塗り薬は、症状のある皮膚に直接塗るものです。
猫がなめてしまわないように注意しつつ、獣医師のアドバイスにしたがって塗布しましょう。
シャンプーによるケア
シャンプーは、原因菌に対して抗菌作用のあるものを使います。
定期的なシャンプーは、細菌の増殖を抑え、皮膚を清潔に保つうえでも効果的です。
ただし、水に濡れることを嫌がる猫も多く、無理に行うとシャンプー自体がストレスになることもあるので注意しましょう。
猫の膿皮症の予防方法

皮膚や被毛を清潔に保つことが基本です。
定期的にブラッシングやシャンプーをすると、皮膚の汚れや余分な皮脂を取り除くことができ、清潔を保つことができます。
ブラッシングの際、皮膚に異常がないかチェックしましょう。
アレルギー疾患がある場合は、アレルギー物質を避けます。
免疫力が落ちないように、ストレスのかからない生活環境を整えることも大切です。
膿皮症は、高温多湿の時期に発症しやすい病気でもあるため、梅雨のころから夏にかけては、温度や湿度の管理にも気をつけてください。
猫の膿皮症への理解を深め対策しましょう
猫の膿皮症は、体力や免疫力の低下、高温多湿などの環境下で、ブドウ球菌に感染したときに発症します。
愛猫に、かゆがるような様子が見られたら、皮膚をチェックしてみましょう。
早い時期に気づいて動物病院で受診し、適切なケアをすれば悪化させずにすみます。
猫の皮膚病につきましては、「猫の皮膚病とは? 症状・種類・対策などを獣医師が解説」でも解説していますので、ご一読ください。
アイペット損保のペット保険は
ニーズに合わせて
2つの商品から選べる