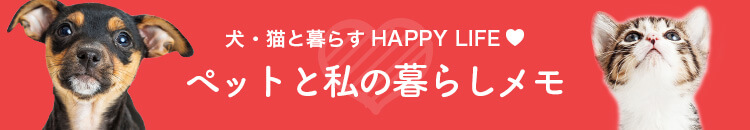子猫の離乳食はいつから?与え方などを獣医師が解説

子猫は、人間の赤ちゃんと同じように、母乳・ミルクから離乳食へと切り替えて成長していきます。
離乳食への切り替えは、子猫の乳歯の生え具合や発育状況などから判断します。
離乳食の与え方も子猫の様子を見ながら変えていく必要があります。
ここでは、子猫に離乳食を与える際のポイントを解説します。
アイペット損保のペット保険は
12歳11か月まで新規加入OK!
ニーズに合わせて2つの商品から選べる
子猫の離乳食はいつから始めるべき?

はじめに、子猫の離乳食を始めるタイミングについて紹介します。
離乳食開始の適切な時期
生まれたばかりの子猫には歯がありませんが、生後3週齢頃になると乳歯が生えてきます。
この乳歯が、離乳食を始める目安です。
自力で排泄できるようになったか、元気はあるかといったことも確認しましょう。
子猫の発育状況など不安があれば獣医師に相談する
子猫に乳歯は生えてきたものの、元気がない、体重が増えないなど健康状態に不安がある場合は獣医師に相談しましょう。
不安のあるまま離乳食を始めないことが、子猫のために大切なことです。
子猫の離乳食の選び方と与え方

乳歯が生え、健康状態に問題がなければ、離乳食を始めましょう。
離乳食の選び方
ミルクだけで過ごしていた子猫のために、初めての離乳食は、かまずに飲み込めるペースト状やムース状のものを選びましょう。
あらかじめペースト状になっているものや、お湯で溶いて与えるタイプだと、やわらかさの調整が可能です。
子猫の成長に必要な栄養素やエネルギーが過不足なく含まれている「総合栄養食」を選びましょう。
離乳食の与え方のコツと注意点
初めて離乳食を口にしたときの子猫の反応はさまざまです。
嫌がる子もいれば、興味を示さない子もいるでしょう。
そのようなときは、離乳食にミルクを混ぜたり、指先に少量の離乳食をつけて口元や鼻先に近づけたりしながら、少しずつ慣らしていきます。
無理をして与えないことが大切です。
子猫は消化機能が未熟なため、食べすぎると下痢をすることがあります。
離乳食を与えた後はうんちも含め、子猫の健康状態に変化がないか観察しましょう。
離乳食の量と頻度の目安
乳歯が生え始めた3週齢~4週齢の頃は、小さじ1杯程度のペースト状の離乳食から始めます。
指先につけた離乳食を口元や鼻先につけるなどして、興味をひいてみましょう。
頻度は3~6時間おき、1日に4~6回程度が目安です。
1度に食べられる量が少ないので、次の回まで時間をあけすぎないように注意しましょう。
この頃はまだ、離乳食だけで栄養をカバーすることはできません。
離乳食の後に、ミルクも与えましょう。
離乳食に慣れてきたら、小皿などの器に入れてにおいをかがせ、自分で食べられるように練習しましょう。
子猫の体調や排泄物をチェックし、問題がなければ少しずつミルクを減らし、離乳食を増やします。
子猫が6~7週齢を迎え、ミルクなしで離乳食が食べられるようになったら、ミルクは卒業です。
離乳食に、ミルクやお湯でふやかした子猫用のドライフードを混ぜて与えるようにします。
目安は、6時間おきで徐々に離乳食を減らしていきます。
8~9週齢を迎え乳歯が生えそろえば、ドライフードをふやかさずに食べられるようになります。
徐々に、ドライフードに移行しましょう。
この頃が、離乳食を終える目安です。
離乳食を終了すると、それまではフードから取っていた水分量を確保できなくなります。
新鮮な水がいつでも飲めるように、水を入れたボウルを用意しましょう。
2~3か所に置くことをおすすめします。
子猫の健康管理と成長促進

離乳食を与えている期間の健康管理や離乳食を終えた後のことを紹介します。
離乳食を与えているときの健康チェック
子猫の消化器官は未熟なため、離乳食期間中に下痢や嘔吐といった症状が出ることも少なくありません。
下痢や嘔吐は、脱水症状につながるので、早めに獣医師に相談しましょう。
また、体重の変化は子猫の成長を知るバロメーターなので、猫用の体重計を用意し、毎日計測するとよいでしょう。
離乳食からフードへの移行
離乳食を終えた後は、バランスの取れた栄養素とエネルギー量が確保できる子猫用の総合栄養食を与えます。
さまざまな味や素材があるので、子猫の食いつきぶりを観察しながら、試してみましょう。
量や頻度は、パッケージの記載にしたがいましょう。
生後12か月頃には、体の成長もひと段落します。
この頃が、成猫用フードへの移行期です。
まとめ
離乳食を始めたばかりの頃は、嫌がったり下痢をしたりすることがあるかもしれませんが、あせらずに進めることが大切です。
健康状態をしっかりと観察して、気になることがある場合は、早めに獣医師に相談しましょう。
アイペット損保のペット保険は
12歳11か月まで新規加入OK!
ニーズに合わせて2つの商品から選べる