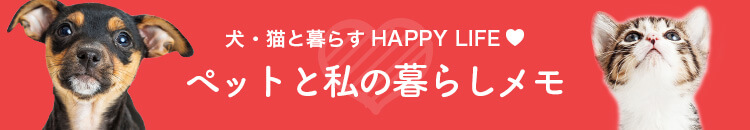子猫が注意したい寄生虫とは? 種類・症状・治療方法などを解説

体の発達が未熟で体力もない子猫の健康を守るために、寄生虫の感染に注意が必要です。
血便や呼吸機能の低下など、重篤な症状につながることも少なくありません。
ここでは寄生虫の種類をはじめ、症状などを紹介します。
アイペット損保のペット保険は
ニーズに合わせて
2つの商品から選べる
子猫が注意したい寄生虫の種類

子猫は特に、免疫系がまだ発達段階にあるため、内部寄生虫に注意しましょう。
子猫が影響を受けやすいとされる内部寄生虫は、原虫(げんちゅう)と、蠕虫(ぜんちゅう)の2種類に分けられます。
原虫(単細胞の微生物)
原虫(げんちゅう)とは、単細胞の微生物をいいます。
猫に多く見られる代表的な原虫としては、「コクシジウム」や「トキソプラズマ」などがあります。
主な感染源は、原虫に感染した猫の便です。
寄生虫の卵や成虫が腸管などにすみつき、便に混ざって体外に出てきます。
子猫が、原虫を含む便を口にしたり、汚染されたトイレをなめたりすると、体内に入り込み感染します。
原虫が寄生しているネズミなどの小動物を捕らえて食べてしまい、感染することもあります。
原虫を含む便で土が汚染されている場合、その土に触れることでも感染するので、注意が必要です。
蠕虫(回虫・条虫・鉤虫など)
蠕虫(ぜんちゅう)とは、ミミズのように手足のない細長い体を持ち、体をくねらせるようにして動き回る寄生虫のことです。
猫が感染しやすい代表的なものとして「回虫(かいちゅう)」「条虫(じょうちゅう)」「鉤虫(こうちゅう)」などが知られています。
感染経路は蠕虫の種類によっても多少異なりますが、主な経路は原虫と同じで、感染している猫の便、捕らえて食べた獲物などです。
母猫が感染している場合は、母乳を通して子猫に感染することもあるほか、条虫のようにノミが媒介するケースもあります。
寄生虫に感染したときの主な症状

寄生虫感染による一般的な症状
寄生虫に感染した場合、一般的には食欲不振、体重減少、嘔吐、下痢、血便、腹部膨満(おなかのふくらみ)といった症状が現れます。
これらは風邪などほかの病気でも出る症状のため、一概に寄生虫感染とは断言できませんが、愛猫のためにも覚えておきましょう。
蠕虫や原虫は採取した便に含まれる寄生虫や卵を確認することで診断できますが、一度の検査では確認できないこともあります。
下痢につきましては、下記の記事でも解説していますので、あわせてご一読ください。
▶関連記事:「猫の下痢はあなどると危険?原因や動物病院を受診するときのポイント」
重篤な症状
寄生虫は腸管に寄生しますが、まれに体内を移動して肝臓や肺に寄生し、呼吸困難などの症状を引き起こすことがあります。
また、嘔吐や下痢による脱水症状は、命に関わる場合がありますので注意が必要です。
治療方法

寄生虫に感染したときは、基本的に駆虫薬を飲ませて治療します。
診断の方法は、問診、便に寄生虫や卵があるかどうかを確認する検査などです。
便検査で明らかに寄生虫が確認できた場合は、薬の効果を判断するため、定期的に通院をして便検査をすることもあります。
一般的に、駆虫薬を投与すれば症状は改善しますが、激しい下痢や嘔吐があるときには、脱水症状を起こしていることも少なくありません。
そういったことも踏まえ、獣医師の判断で、水分やミネラル分を補給する点滴を行うこともあります。
猫を寄生虫に感染させないための対策

猫の寄生虫対策では、早い時期からの駆虫薬投与が効果的です。
猫をお迎えしたら、なるべく早く動物病院を受診し、予防薬について相談するとよいでしょう。
その後も定期的に健康診断を受けることが、寄生虫感染の予防になります。
子猫が母猫やほかの猫と過ごす環境にいる場合は、しっかりと便の処理をして感染拡大を防ぐことも大切です。
猫の排泄が済んだら、早めに便を取り除き、常にトイレを清潔に保つようにしましょう。
飼い主さまが愛猫と触れ合った後やトイレの掃除をした後は衛生に配慮し、必ず手を洗うことも大切です。
食事では、栄養バランスに気をつけて、寄生虫に負けない体づくりをサポートしましょう。
特に免疫力も体力も十分についていない子猫の場合は、大切なポイントです。
日常的に猫とコミュニケーションをとり、食欲や便の様子をチェックする習慣をつけると、体調不良にも気づきやすくなります。
また、定期的な便検査で、目に見えない寄生虫の有無を確認することも重要です。
まとめ – 子猫の寄生虫感染は特に注意しましょう
猫が寄生虫に感染すると、食欲不振、体重減少のほか、嘔吐、下痢や血便などの症状が現れます。
免疫力も体力も弱い子猫は特に脱水のほか、肝臓や肺にも影響が及ぶなど重篤な症状につながりかねません。
猫をお迎えしたら早めに動物病院で健康診断を受け、寄生虫に感染しないように気をつけてケアをしていきましょう。
アイペット損保のペット保険は
ニーズに合わせて
2つの商品から選べる